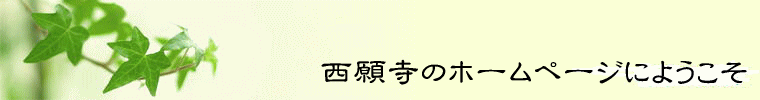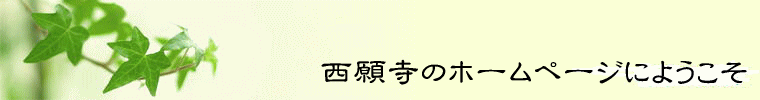| ���莛�R�� |
�T�@�O�h�i�����@�A�ՍϏ@�A���@�@�j�̈�ł���A
1654�N�ɗ������ꂽ�����m�B���T�t�ɂ���đn�����ꂽ���@�R�ݕ���(���s�{�F���s)��{�R�Ƃ���B
���m�̈�l�u��،o�v�̖ؔł���삳�ꂽ�S��T�t�̌Z��q�ŁA
���R�����Ɍ��т��c���ꂽ�S���T�t���J�R�Ƃ���B
�勝�R�N�i1686�j12���S���T�t�̖@�k���B�T�t�����̎u���p���A����R�[�̑�n�ɂ����Ē��v�ۏ�ՂƕS��k�J�����Ăđ�����`���̒n�ɓ�����n�����ꂽ�B
�ȗ��V��܂Ŏt���p���������A�V�ۂW�N�ȗ����Z�ɂȂ�
�Éi�Q�N�i1849�j�X���{�R�ǒ��̓����ɂ��L�בT�t���W�R���A
�����W��ƂȂ�ɗ��{���A���甪���Ђ��Č���������B
��㎛�^�ܒ����]�S�ʊJ�������B
1952�N�A��������{���������B
2016�N�A�ʔv���������B
|
| Wikipedia�u���莛�i���j�v�̃y�[�W�� |
| ���@�@�Ƃ� |
�y�R���z
1654�N�B�����g�T�t�i1592�`1673�j���n���B
�B���T�t�͖��㖖�̒����ɂ�����Սόn���̑T�@�̏d���ł��������A����̉؋��ɐ���ꗈ�������B
���̌�A����S�㏫�R�E�ƍj���R�鍑�F���i���s�j�Ɏ��̂������A���@�R�ݕ�����n�������B
�y�����̓����z
�l�Ԃ����܂�Ȃ���ɂ��Ď����Ă��镧�S���A���T�s���s�Ȃ����Ƃɂ���āA����̗͂Ō��o���A���ɂƓ��l�̋��U��̓������悤�Ƃ���B
���퐶���ɂ�����ꋓ���������āA���ɂ̐��E�߂Â��悤�Ƃ��鐸�i�i�w�́j���ꂪ��Ȃ̂��Ɛ����B
�ՍϏ@�̏@���ɖ���̔O���T���������B���T�t�̋����́A������y��O���Ȃǂ̏�y�����`�����킹�Đ����āA�O�T��v���͂������ŁA�^���ɗ���Ȃǂ̖����I�v�f���������Ă���B
�܂��A�{��̓��C�i�Ƃ�����j�ɂ���u�o�́A���̓Ɠ��̐߉ŁA�u���S�i�ڂ���j�v�ƌĂ�A���@�@�̓����I�Ȃ��̂ł���B |
| ���@�@22����b�ɂ��� |
| ���ē� |
 |
| ���F��������������u�܊ρv�@�E�F���莛���u��ߓa�v |
| �����Ƃ�
���@���Q�q���A�ʌo�܂��͓njo��[�߂��Ƃ��Ď����̂��{���̈Ӗ��ł���A�u�[�o��v�Ƃ������Ă��܂��B
�����ł͂�����t�Ɂu�\�����ʌo�v�����p�ӂ��Ă���܂��̂ŁA���̏�ł̎ʌo�E�[�o�����邱�Ƃ��o���܂��B
����͌ɗ��̌��ւɂĎ�t�������܂��B
�s����@���ɂ��s�݂ɂȂ鎖������A�Q�q�̂��߂����J�����A����������ߒ����Ă����Ή��ł��Ȃ����Ƃ��������܂��B
|
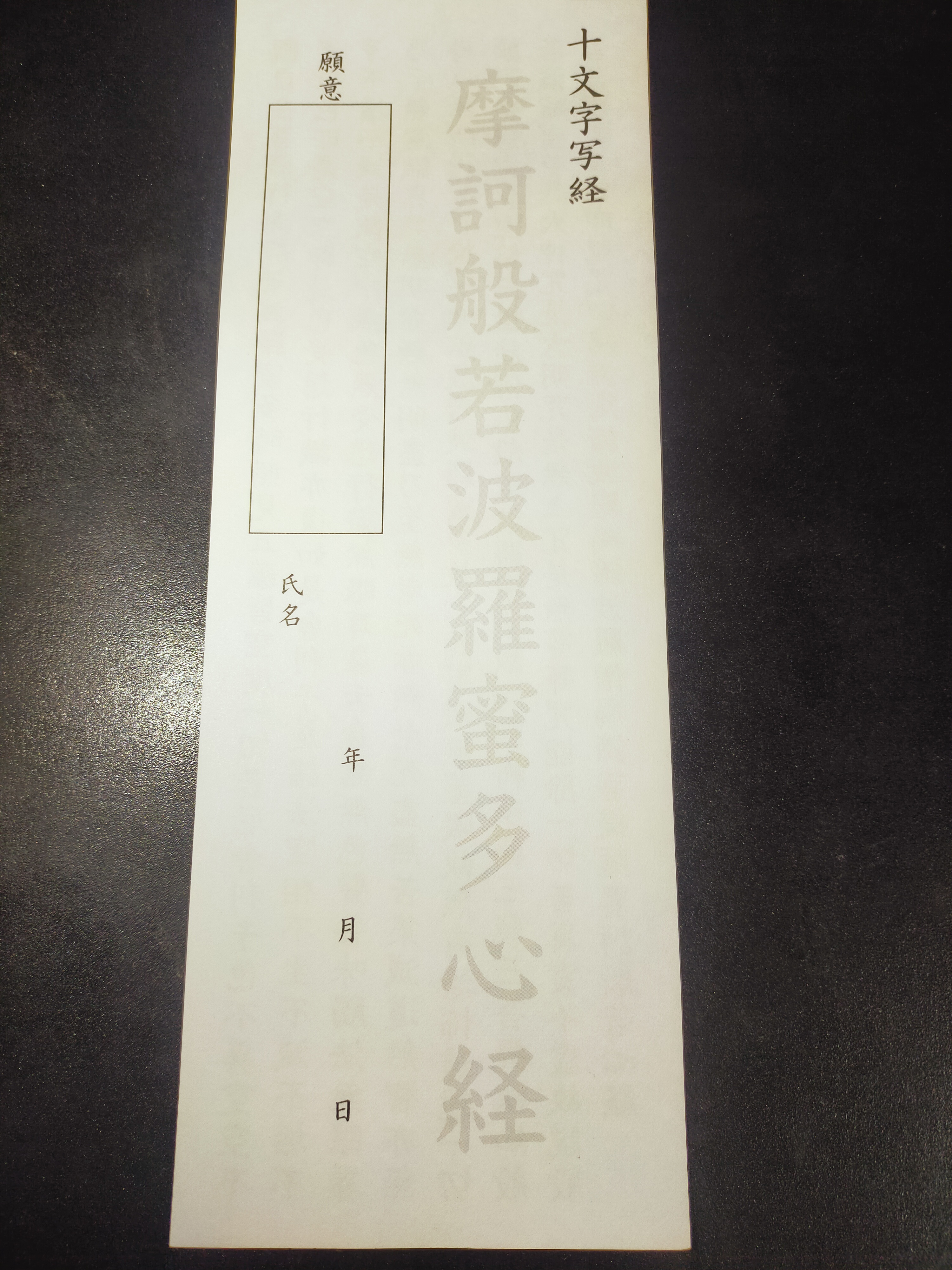 |
| �\�����ʌo�F�ʌo�����Y��̏ꍇ�ł��[�o���o���܂� |
| �����ē� |
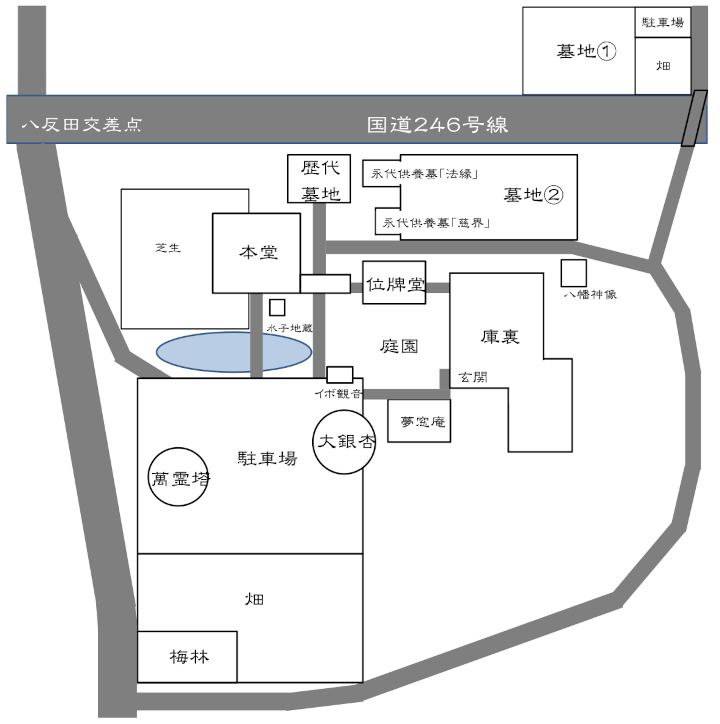 |
| ��ʁE�A�N�Z�X�̂��ē� |
�傫�Ȓn�}�Ō��� |
|
| �A�N�Z�X�K�C�h |
| �Ԃł��z���̕� |
| ���������ԓ����� |
�V���������ԓ����� |
�ɓ��c�ѓ����� |
| ����IC���� |
��10�� |
�������IC���� |
��10�� |
����IC���� |
��5�� |
|
| �d�ԁE�o�X�ł��z���̕� |
���C���V�����E���C�����@
�O���w���� |
��a����@
����Ȃ߂�w���� |
| �y�^�N�V�[�𗘗p�z |
�y�^�N�V�[�𗘗p�z |
| �^�N�V�[���ꂩ�� |
��10�� |
�^�N�V�[���ꂩ�� |
��5�� |
| �y�o�X�𗘗p�z |
�y�o�X�𗘗p�z |
�x�m�}�V�e�B�o�X
����Z���^�[�E�x�͕��E���� ����
�����E�o�X��ɂĉ��� |
��20�� |
����E�����z�o�X
�É���ÃZ���^�[����
�����E�o�X��ɂĉ��� |
��10�� |
| �����E�o�X�₩��k����5�� |
| �� �~�܂�Ȃ��o�X������̂Ŏ��O�Ɂ@�y������@�o�X�H���}�E�����\�z�@�Ŋm�F���Ă������� |
|
���莛�ւ̒n�}�����䗘�p��������
�����炩�������Ă�������
|
|
���ݒn
��411-0934
�����x���S�������E386
�d�b�ԍ��@055-986-1411
|